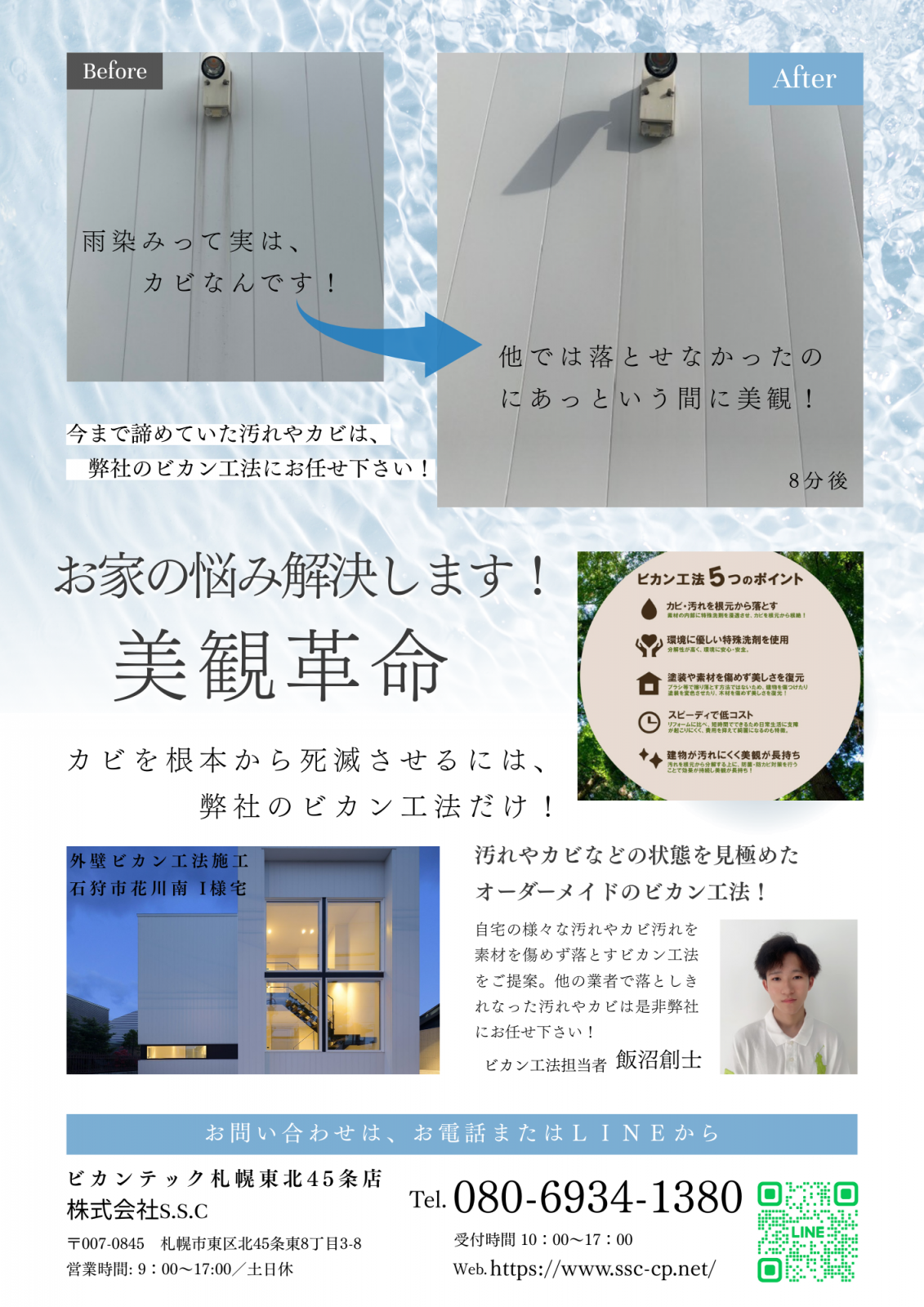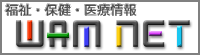| 居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費) |
これまで住み慣れた自宅でも、介護が必要な状態となると生活がし難くなる場合も少なくありません。手摺り(てすり)をつけたり、段差をなくしたりする住宅改修をすれば引き続き生活ができる場合がありますが、介護保険では住宅改修の費用について20万円を上限として給付されます。
要支援でも要介護でも在宅サービスの支給限度額とは別枠で利用できます。
自己負担は費用の1割、給付は原則1回
自己負担は費用の1割です。費用が20万円を越える場合は、20万円の1割である2万円と20万円を越える分が利用者の負担となります。
住宅改修の見積もりで20万円を越えた場合、自治体独自の住宅改修補助制度を利用することができればこれを合わせて利用することで利用者負担を抑えることができます。
住宅改修費20万円の支給は原則1回ですが、要介護度が著しく高くなった場合や転居した場合は、再度利用できる場合があります。
住宅改修費の支払いの方法は、償還払い方式(まずは利用者が費用全額を支払い、後から自治体が9割を償還)と受領委任払い方式(認可を受けた事業所を利用する場合、はじめから1割の負担で行える)があり、自治体により異なります。
改修工事の前に申請を
介護保険で住宅改修をするには、改修工事の前に市町村の窓口に申請をする必要があります。事前に申請をすることなく改修をした場合は、介護保険からの給付の対象とならないので注意が必要です。
介護保険の対象となる住宅改修については表を参照して下さい。
 |
居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)Q&A
Q.自宅にリフォーム業者が来て、「介護保険証を持っていれば、フローリングなどのリフォームが無料でできますよ」と勧められました。本当ですか。
A.介護保険のサービスはすべて、介護保険証を持っているだけでは使えません。要介護認定を受けて、要介護度を元にケアマネジャーが立てるケアプランに沿って使うものです。福祉用具購入・住宅改修のような、ケアプランがいらないサービスでも、要介護認定は必ず受けなければいけませんし、ケアマネジャーの理由書も必要になります。
Q.居間のサッシの、ガラスが割れてしまった。「扉の取替」に当てはまると思うので、介護保険で直してほしい。
A.破損した部分の修理や取り替えは、介護保険の給付には認められません。介護保険で取り付けた手すり等でも、「受け金具が外れたので修理したい」といった、修理・修繕の場合は介護保険の対象外です。
Q.玄関に手すりを取り付けたいが、日曜大工の得意な息子がいるので、材料だけ買ってきて息子に付けてもらおうと思う。家族が取り付ける場合は、介護保険の対象にならないのか。
A.被保険者が自分で材料を購入し、本人または家族等によって住宅改修が行われた場合には、材料費のみが支給対象となります。この場合、支給申請の添付書類として、材料の販売者が発行した領収書(レシート不可、宛名が「上様」等は不可)に加えて、使用した材料の内訳を記載した書類を、本人または家族等が作成し提出する必要があります。
Q.玄関が狭くて車いすで出入りできない。寝室の掃出し窓から出入りするためスロープをつけたいのだが、住宅改修として認められるか。
A.玄関でない場所でも、本人が日常生活上出入り口として使用するのであれば、改修箇所として認められます。
Q.要介護認定を受けている祖母を家に引き取って同居するので、祖母が寝起きする部屋を増築したい。
A.新築・増築は、介護保険の支給対象としては認められていません。したがって、手すりの取り付け等、支給対象になっている内容の改修であっても、新築・増築時に、その新築・増築部に同時に施すことは対象外になります。
Q.介護保険の住宅改修は、1回20万円が上限と聞いた。この20万円を何回かに分けて使うことはできないのか。
A.介護保険の対象となる住宅改修は、20万円を改修総費用の上限として、その9割が保険給付されます。この20万円の枠は、基本的には一人一生涯に対してのものですので、「最初は10万円で手すりをつけて、後から残りの10万円で段差解消する」というように、数回に分けて使うことも認められています。この場合は、改修を行うその都度、支給申請を行ってください。